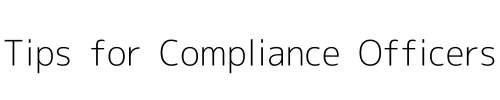投資運用関係業務受託業が制度として走り始めて約半年が経過します。現時点では、1社がその登録を受けています1。制度を大まかに述べれば、「投資運用業者は計理業務またはコンプライアンス業務またはその双方(合わせて投資運用関係業務)を投資運用関係業務受託業者に委託可能。そして投資運用業の登録要件(人的構成要件)の一部緩和を受けられる」というものです。
制度の目的は、これから投資運用業に参入する社の「負担軽減」だと思っています。投資運用業の計理には専用のシステムが必要であり、投資運用業は投資家保護や法令順守のためにコンプライアンス部門が必要です。しかし、計理部署やコンプライアンス部署は投資運用業者にとって必要であっても目的ではありません。「コンプラ疲れ」という言葉があるように、敵と見られてしまうコンプライアンス部署です。筆者は社内にコンプライアンス部が必要との立場ですが、かつて筆者が所属した企業ではコンプライアンス部に他部署から不満が募っていました。
まず、筆者が見聞きしたコンプライアンス部署への不満を列挙します。続いて、仮にコンプライアンス部署が社内に無い場合のマイナス面を記載します。最後にコンプライアンス・オフィサーである筆者が日々気を付けている事項を共有します。
コンプライアンス部署への不満
アセットマネジメント業界における筆者のコンプライアンス部署経験は15年目になりました。直接言われた文句&コンプライアンス部にぶつけられた不満の一部です。
① 否定しかしない。発言や態度がビジネスに即してない
② 相談してもめんどくさそうor「自分で考えてください」という返事
③ ルールをわかってない気がする
④ 偉そう。評論家。手を動かさない
⑤ 問題解決のための会議をつるし上げの場だと思っている
人間関係なので双方に言い分はあると思うのですが、「上から目線で手を動かさない、聞く耳の無い攻撃的な人」が嫌われるのは当然です。①-⑤の背景を分析するのは当ブログの目的ではないのですが、私見を書きます。原因は、そのコンプライアンス・オフィサーの専門性の欠如です。
日本の金融機関では、コンプライアンス部署や内部監査部署は「上がりの部署」であり、定年退職までの腰掛けでした。コンプライアンスは本来、法令に対する正確な理解とそれをビジネスに当てはめる応用力、課題を解決するための創造性が必要です。これらは決して短期間では身につきません。そして、法令も社会が求める「正しさ」もアップデートされていくので絶えず学び続ける義務があります。知識を使って人の役に立ちたいという気持ちがコンプライアンス人材の根幹であり、その集まりたるコンプライアンス部署は絶対に「引退までの残り時間を消極的に過ごす部署」ではありません。
①ー⑤の人物には何の専門性もありません。質問されても答えられないので、質問者に責任を転嫁しているだけです。誰かの過失を見つけて盛り上がっているのでしょう。①-⑤をコンボで決めてくる人が極力少ないのを願っていますが、構造的にコンプライアンス部にはそういう人物が生息する土壌があります。
もしもコンプライアンスを外部委託したら
ストレスの原因であるコンプライアンス部をアウトソースしたら投資運用業者の仕事がバラ色になるかというと筆者は否定的です。理由を記載します。
①コンプライアンス上の責任は委託元に残り続ける
投資運用関係業務受託業者にコンプライアンス業務は委託できますが、コンプライアンス責任は委託元に残ります。投資運用業者の登録要件を見ても、委託するコンプライアンス業務を監督する者は委託元に存在しなければなりません2。(登録の拒否要件に列挙されており、満たせなければ投資運用業者としての登録が成就しないです)
委託先がコンプライアンス業務を遂行しきれなかった際に、委託元が急に”お客様”になって委託先を責めるのは不可です。信じて任せた判断の責任を負わなければなりません。
②利益相反管理
刻々と株式市場が動いている中、アラジンからアラートが上がりました。委託先のコンプライアンス業務担当者はアラート解除可否の判断をしなければなりません。1人がその瞬間に対応できる案件は1件ですが、複数のアセットマネジメント会社のアラートが同時に上がったら、どれから優先して対応するのでしょうか?後回しになった会社は市場価格の変動リスクを取らされています。
投資運用関係業務受託業者と委託先は1対1でなければならないという規制はありません。ある1社から知った情報を他社の業務に利用しないのを納得感ある形で担保してもらえるでしょうか。
③責任の所在
コンプライアンス上の大きな問題が起きたら、双方が相手の非を主張するかもしれません。「問題の原因は委託元の指示の曖昧さにある。今回の業務は委託の範囲に入っていない。」「いや、委託契約書は完璧だった。読み違えた委託先が悪い」「いいや、そもそもこの契約条文は無効だ。」こういった水掛け論は起きないでしょうか。受益者や一任顧客にしてみれば、正直どっちでもいいです。責任の軽重を巡って議論が紛糾している間は賠償は行われず、投資家にコストが生じています。
社内にコンプライアンス部があれば、会社とコンプライアンス部は一体です。筆者はこの一体性(責任逃れのできなさ)に誇りを持っています。投資家保護に加えて、会社を守るためにも仕事をしている誇りです。
筆者が普段気を付けている事項
コンプライアンスそれ自体はどれだけ万全にしても収入が増えるわけではありません。筆者のプロファイルを人事システムで確認すると、所属欄に「Divison:Compliance(Cost Center)」と書いてあります。
収益を追求する株式会社がなぜ私を社内に置いているのか?きっと意味があると思うのです。私なりの思いに基づいて、日々行動している事項を挙げます。
① 毎日出社する
誰かがコンプライアンス部に相談に来る時は、判断に迷ったり、まずい事態が起きそうだったり、もう起きている時です。困った時にデスクに行けばコンプライアンス・オフィサーがいるのは安心感につながると信じています。後述の②ー④を通じて、話を聞いてくれ、力になってくれる人であるという信頼も積み重ねています。
② 相談者が来たら作業を止めてその人の方に体ごと向けて顔を見る
せっかく相談しに行ったのに、めんどくさそうにされたり、話を聞いてもらえなかったら正直関わりたくないです。そして私の信頼貯金も失います。
③ 提案だけではなくドラフトもする
特に社内手続きを変える時は、こうしたらいいと口で言うだけでなく、ポイントをメモに書き出して渡すようにしています。重い案件であれば、マネージャーに報告した上で、改定案を書いた時もありました。
要点をメモに書き出すと、自分の思考も整理されます。相手と一緒に見るものだから、わかりやすい説明を心がけるインセンティブにもなります。そして、多くの場合相手はこのメモが欲しいと言います。メモを見る度に私を思い出してもらえるので、いい印象付けにもなります。
④ 営業部や運用部の業務理解に努める
手続書を読むという基本に加えて、2つのアプローチを使っています。1.相手は誰に評価されると嬉しいのか/叱られると困るのか 2.何か課題が解決した後に相手に「今振り返って見て、どうしたら私はもっと力になれたか」聞くようにしています。軽い案件で、コンプライアンス上の意見だけを求められて案件が私を離れてしまっても、課題が決着したら「あの件は最後はどんな顛末だったか」聞きます。そして、顛末から要点と要点のうち私ができたであろうポイントを逆算します。
企業のコンプライアンス部はその企業のために存在します。コンプライアンス部のクライアントは社内の全部署です。クライアントを完全に理解できずとも、理解しようと努力し続ける責任がコンプライアンス・オフィサーにはあります。
まとめ
コンプライアンス部署は社内に必要という考えに一点の曇りもありませんが、合理化は資本主義社会の当然です。投資運用業において、コンプライアンス業務は無くなりません。でも、筆者がその仕事を続けられるかは絶えず検証にさらされています。
コンプライアンス上の助言に限らず、アドバイスの価値は、「何を言うか」と「誰が言うか」の掛け算の結果だと考えます。絶えず知識をアップデートすることで、専門性を向上させて内容のある言葉を伝えたいです。そして、聞く耳を持ち、人の助けになってその「誰」に値する者でありたいです。
- https://www.fsa.go.jp/common/shinsei/im-rs/index.html ↩︎
- 金商法第29条の4(登録の拒否)第1項第1号の2ただし書「業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」 ↩︎